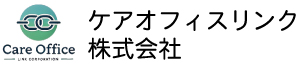士業の先生方(弁護士・税理士・司法書士など)は本来、専門サービスの提供が本業です。
しかし事務所運営では、経理・総務といった裏方作業にも多くの時間を割かれてしまいがちです。
そんな士業事務所の経営者の皆様は、日々のバックオフィス業務に頭を悩ませていないでしょうか?
専門業務で忙しい中、経理処理や労務手続きといった事務作業にも時間と労力を割かなければならず、事務効率が下がってしまうケースが散見されます。
特に小規模な士業事務所では、人手不足や業務の属人化により、バックオフィス業務が滞りがちです。
近年、こうしたバックオフィス業務改善の重要性が増しており、ITツールの活用やアウトソーシング(業務代行)によって大きな効果が得られるようになってきました。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れに乗り、こうしたバックオフィス改革は小規模な事務所でも十分に実現可能です。
本テーマでは、士業事務所が抱えるバックオフィスの課題に触れつつ、経理・労務業務の効率化ポイントと、業務をプロに任せるメリットについて解説します。
士業事務所のバックオフィス業務課題
士業事務所が直面するバックオフィス業務の課題として、まず 業務量の多さ が挙げられます。
小さな事務所であっても、請求書の発行や経費精算、帳簿付け、勤怠管理、給与計算、社会保険の手続きなど、経理・労務に関する雑多な業務が日々発生します。
これらは直接収益を生む業務ではないものの、怠れば事業運営に支障をきたす重要な役割です。
しかし、専門スタッフを十分に配置できない士業事務所では、こうした間接業務が人手不足の中で回らなくなり、担当者に過度な負担がかかりがちです。
次に業務の属人化の問題も見逃せません。特定の職員だけが経理や労務のやり方を把握している場合、その人が不在になると業務が滞ってしまいます。
また、引き継ぎがうまく行われていないと、新任スタッフが何から手を付ければいいかわからず、業務改善が進まない原因にもなります。
実際の調査でも、バックオフィス担当者の課題として「人手不足」(34.7%)や「属人化」(30.8%)が上位に挙げられており、こうした問題は多くの事務所で共通しています。
さらに、アナログな作業が多い点も課題です。
紙の書類やエクセルでの管理が中心だと、入力ミスや二重入力が起こりやすく、全体的な作業効率を下げてしまいます。
実際に、ある調査では経理担当者の約半数が毎月10時間以上を紙の書類対応に費やしているとの結果もあり、紙中心の運用が業務効率を圧迫している実態が浮き彫りになっています。
このように士業事務所ではバックオフィスの負担が大きく、事務効率の低下やミスによるトラブル(例:期限までに申告・届出が間に合わない、給与計算ミスによる従業員からの苦情)が起こり得ます。
そこで求められるのが、経理・労務の業務フローを見直し、IT化や外部活用によってバックオフィス業務を効率化する取り組みです。
次章から、具体的な経理および労務の効率化ポイントを見ていきましょう。
経理業務効率化のポイント
経理業務を効率化するためには、ITツールの活用とアウトソーシングの二つが大きなポイントとなります。
まずITツールについて言えば、会計ソフトのクラウド化が非常に有効です。現在は freee(フリー) や Money Forward(マネーフォワード) などオールインワンのクラウド会計ソフトが広く普及しており、請求書発行から日々の仕訳入力、経費精算、さらには給与計算まで一元管理できます。
たとえば銀行口座やクレジットカードの明細データを自動連携して取引を自動記帳したり、領収書をスマホで撮影してAIが読み取ってくれるOCR機能を使ったりすることで、手入力の手間を大幅に削減できます。
また、クラウド上でデータが共有されるため、事務所内のどこからでもアクセスでき、税理士など外部の専門家ともリアルタイムで情報を共有可能です。
これにより、経理業務のタイムリーな遂行とミスの減少が期待できます。
さらに、帳簿類や書類の電子保存が進むことで、紙の保管スペース削減やバックアップの容易さといったメリットも享受できます。
近年開始された適格請求書等保存方式(インボイス制度)や改正電子帳簿保存法などへの対応という面でも、クラウド会計ソフトを導入しておけばスムーズに電子化が行え、法令遵守を確実にしやすくなります。
次にアウトソーシング(業務代行)の活用です。
クラウドツールを導入しても、自社でその運用まで手が回らない場合、思い切って経理業務を専門のサービスに委託するのも有効な手段です。
専門のバックオフィス代行サービスに依頼すれば、日々の記帳・振込業務から月次決算の取りまとめ、帳簿チェックまで、煩雑な作業をプロに任せることができます。
専門スタッフに任せることで作業スピードが上がり、最新の会計知識に基づいた正確な処理が行われるため、品質向上にもつながります。
また、アウトソーシングは自社で人材を雇用するよりもコストを抑えられる場合が多く、必要なタイミングで必要な分だけサービスを利用できる柔軟性も魅力です。
経理部門の無い士業事務所でも、こうした外部の力を借りることで安心して本業に集中できるでしょう。
労務業務効率化のポイント
次に、人事・労務関連の業務効率化について見てみましょう。
勤怠管理や給与計算のデジタル化が第一のポイントです。
タイムカードや手書きの出勤簿で社員の勤怠を管理している場合、専用のクラウド勤怠システムへの移行を検討すべきです。
従業員が各自PCやスマホから打刻できるシステムを導入すれば、勤務時間データが自動で集計され、残業時間や有給休暇の管理も一目で把握できます。
このようなデジタル管理は、近年強化されている労働時間の適正管理(働き方改革関連法への対応)にも役立ち、法令遵守の面でも安心です。
そしてその勤怠データと連動した給与計算ソフトを使えば、毎月の給与計算がボタン一つで完了します。
給与から控除すべき税金や社会保険料率も最新の法令に合わせて自動計算されるため、計算ミスを防げます。
クラウド型の人事労務ソフト(例:freee人事労務やマネーフォワードのクラウド勤怠・給与など)を活用すれば、給与明細の電子配布や年末調整の自動化も可能となり、労務管理全体が大幅に効率化されるでしょう。
次に社会保険手続きの効率化です。
社員の入退社に伴う健康保険・厚生年金の加入喪失手続きや、育児休業の給付申請、年度ごとの算定基礎届・労働保険年度更新など、社労士(社会保険労務士)でなくとも対応が必要な手続きが多々あります。
これらを毎回紙の届出用紙で行っていると、役所への届出に出向く手間や記入ミスのリスクが発生します。
そこで、電子申請システムやソフトを活用して社会保険・労働保険の各種届出をオンライン化することが有効です。
電子政府のe-Govなどを使えば、事務所からオンラインで届け出ができ、処理状況も画面上で確認できます。
ただし電子証明書の取得やシステム設定に手間取るケースもあるため、小規模事務所では必ずしも自前で電子申請環境を整えなくても、専門家に委託する方法もあります。
最後に外部の専門家・サービスの活用です。
先述の通り、社労士に相談することで複雑な手続きを代行してもらったり、最新の法改正情報に基づいたアドバイスを受けたりできます。
また、給与計算や社会保険事務を請け負うアウトソーシングサービスを利用すれば、毎月の勤怠集計から給与支給、年次の各種申告まで一括して任せることも可能です。
信頼できる外部支援を得ることで、煩雑な労務管理から解放され、士業の先生方は本来の専門業務により専念できる環境が整います。
バックオフィス業務をプロに任せるメリット
最後に、バックオフィス業務を外部のプロフェッショナルに任せることの主なメリットを整理します。
◆迅速な対応と業務品質の向上
専門サービスに依頼すると、経験豊富なスタッフが担当するため、対応が迅速です。
自社内で手が回らず後回しになっていた処理も、プロなら計画的かつスピーディーに進めてくれます。
また、専門知識に基づいた正確な業務遂行により、ミスが減り品質が向上します。
◆全国対応など柔軟なサポート
外部のプロに依頼すれば、地理的な制約を超えて支援を受けられる柔軟性があります。
近年、普及しているリモートツールなどを活用すれば、所在地に関係なくサービス提供が可能なため、地方にある事務所でも安心してアウトソーシングを活用できます。
◆コア業務に専念できる
煩雑な経理・労務から解放されることで、士業事務所の経営者やスタッフは本来の専門業務に集中できます。
例えば、バックオフィスを専門会社に委託した結果、残業時間が大幅に減少し、生まれた時間を新規顧客開拓に充てられるようになった事務所もあります。
本業に専念できれば顧客サービスの向上や付加価値の高い業務に時間を投下でき、結果として事務所全体の生産性向上と業績アップにつながります。
◆コスト面のメリット
バックオフィス業務を内製で賄おうとすると、人件費や教育コスト、ITシステム導入費など様々な固定費がかかります。
これをアウトソーシングに切り替えれば、必要なときに必要な分だけの費用で済ませることができ、無駄なコストを削減できます。
また、自前で全てを行う場合と比べて、プロのスキルや既存の仕組みを活用できる分、コストパフォーマンスに優れるケースが多いです。
さいごに
士業事務所におけるバックオフィス業務の効率化は、もはや選択ではなく必要不可欠な取り組みと言えます。
経理・労務の事務効率を上げることで、本業に集中できる環境を整え、サービス品質の向上や事務所の発展につなげることができます。
そのためには、今回ご紹介したようなクラウドツールの導入や業務代行の活用を積極的に検討すべきでしょう。
重要なのは、自社の状況に合った解決策を選び、信頼できる外部パートナーを見つけることです。
その際には、相手企業のサービス内容や実績、対応力などを十分に確認し、ご自身の事務所のニーズに合致するか見極めることが大切です。
バックオフィス効率化の経験と実績があるプロフェッショナルと連携すれば、安心して業務を任せることができ、効率化プロジェクトを着実に進められます。
この最適化への取り組みによって、冒頭で触れたバックオフィス業務の悩みから解放され、事務所運営にゆとりと成長の余地を生み出すことができるはずです。
士業事務所の経営者にとって、頼れるパートナーとともにバックオフィス最適化に取り組むことが、これからの時代を生き抜く上で大きな武器となります。
ぜひこの機会に経理・労務業務の効率化に踏み出し、貴事務所のさらなる発展につなげてみてください。
2025年4月17日 カテゴリー: 未分類