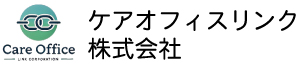健康経営への注目が全国的に高まる中、福岡の企業でも社員の健康づくりへの取り組みが重要な経営課題となっています。
実際、経済産業省が推進する「健康経営優良法人」の認定企業数は年々増加しており、2025年には大規模法人で3,400社、中小規模法人で19,796社もの企業が認定されました。
社員の健康管理を戦略的に進めるこの健康経営は、生産性向上や医療費削減など企業にも多くのメリットをもたらすとして注目されています。
本テーマでは、福岡市内に本社を置くA社の事例を交え、従業員の栄養管理に焦点を当てた健康経営の具体策とその効果をご紹介します。
管理栄養士と連携した社員健康サポートの成功ポイントを探り、福岡の人事担当者・経営者の皆様に役立つヒントをお届けします。
健康経営とは何か?福岡企業が注目すべき理由
まず「健康経営」とは何か、その基本を確認しましょう。
健康経営とは、企業が従業員の健康管理を経営戦略に組み込み実践する取り組みです。
社員の健康状態を改善し生産性を向上させるとともに、超高齢社会に対応して健康寿命の延伸を図る経営手法として始まりました。
実際に優れた取り組みを行った企業は経済産業省などによる「健康経営銘柄」選定や「健康経営優良法人認定制度」に認定され、公的な評価を受けています。
福岡県でも、この流れに沿って企業の健康づくりを支援する施策が展開されています。
例えば、福岡県はふくおか健康づくり県民運動を推進し、社員の健康増進に積極的な事業所を登録・紹介する制度を設けています。
また、九州経済産業局や地元経済団体も参加する「九州・福岡健康経営推進協議会」が発足し、地域に根ざした健康経営の普及に努めています。
こうした背景から、福岡の企業にとって健康経営に取り組む意義は非常に大きいと言えるでしょう。
健康経営を導入することで、企業はさまざまなメリットを得られます。
前述の通り、生産性の向上や長期的な医療コストの削減といった投資効果が期待でき、従業員にとっても働きやすい職場環境が整備されます。
また、健康経営に熱心な企業であることは、求人市場においても企業イメージ向上につながります。
実際に、最近では求人情報に「健康経営優良法人認定」をアピールする企業も増えており、求職者や取引先からの評価アップにも寄与するのです。
従業員の栄養管理が健康経営の鍵に
数ある健康経営の取り組み分野の中でも、従業員の食生活・栄養管理は重要な柱の一つです。
忙しい現代のビジネスパーソンは、つい食生活が疎かになりがちです。
実際に
「昼食は仕事の合間にコンビニのおにぎりや菓子パンで済ませている」
「朝食を抜いてしまう」
「野菜や果物をほとんど食べない」
といった従業員を抱える企業は少なくありません。
こうした偏った食生活が続くと、栄養不足や過多による肥満・生活習慣病リスクの増大、さらには午後の生産性低下や集中力欠如など、業務面にも悪影響が及びます。
社員の健康を維持しパフォーマンスを最大化するためには、栄養バランスの取れた食事を促すことが欠かせません。
企業が従業員の栄養管理を支援することは、健康経営の評価項目にも含まれています。
経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」では、具体的な食生活改善の取り組みとして次のような項目が推奨されています。
・管理栄養士または栄養士が管理する社員食堂の設置・運営
(専門家の監修による栄養バランスの良いメニューを社員に提供)
・栄養バランスに配慮した弁当・食事を提供する環境整備
(社員が健康的な食事を選びやすいよう社内で仕組みを用意)
・食生活改善に役立つアプリや記録ツールの提供
(日々の食事内容を記録・可視化し、自己管理を促進)
・管理栄養士や外部専門家による栄養指導・相談窓口の設置
(社員が個別に食生活の悩みを相談できる仕組みづくり)
・第三者認定を受けた健康的な食事(例:スマートミール)の提供
(ヘルシーなメニューを社食や仕出し弁当で導入)
・朝食欠食者への対策(朝食提供等)
(朝食を摂る習慣づけや朝食代補助などの施策)
このように社員の食生活改善に関する取り組みは多岐にわたり、企業の健康経営を語る上で欠かせない要素となっています。
栄養面のサポートなくして、真の意味で社員の健康増進を図ることは難しいでしょう。
特に福岡はグルメな土地柄でもありますが、だからこそ職場での栄養管理支援が社員の生活習慣を整える一助となり得ます。
管理栄養士と連携するメリットとは
では、こうした食生活改善を進めるにあたり、管理栄養士と連携することにはどんなメリットがあるのでしょうか。
管理栄養士は栄養の専門家であり、社員の健康状態やニーズに合わせた的確なアドバイスができる心強いパートナーです。
企業内に専門知識を持つ管理栄養士がいることで、次のような効果が期待できます。
社員食堂メニューの最適化
管理栄養士の知見を活かし、社食のメニューを野菜中心にしたり塩分・脂質を控えめにするなど、健康に配慮した食事提供が可能になります。
実際に、ある企業では「揚げ物メニューの価格を上げ、魚料理の価格を下げる」工夫で社員の摂取脂肪量を減らす取り組みを行いました。
専門家の監修による食事提供は、社員の食習慣を無理なく好転させる効果的な手段です。
個別栄養指導とフォロー
社員一人ひとりの健康課題(メタボリックシンドローム予備群、高血圧、貧血傾向など)は異なります。
管理栄養士が定期的に個別面談を実施すれば、各自の食事内容をヒアリングし、改善ポイントをアドバイスできます。
例えば計測機器メーカーのタニタでは、早くから管理栄養士によるメタボ社員への個別指導を導入し、大きな成果を上げました。
その結果、健康診断でメタボリックシンドロームと判定された社員の人数が96名中16名から7名へと半減した例も報告されています。
このように専門家によるきめ細かな指導は、社員の健康改善を着実に後押しします。
健康教育・セミナーの実施
管理栄養士が講師となり、社内で栄養に関するセミナーやワークショップを開催することも有益です。
栄養バランスの重要性や食習慣と生活習慣病の関係などを啓発し、社員の健康意識を高める機会になります。
実際、福岡県内でも企業向けに栄養セミナーを提供する団体や専門家が増えており、そうした外部リソースを活用する企業も出てきています。
継続的な食の教育は、社員の行動変容(健康的な選食や適切な食事量の習慣化)につながり、長期的な健康増進に寄与します。
社員のモチベーション向上
専門家と連携した取り組みは「会社がそこまで自分たちの健康を気遣ってくれている」という安心感・満足感を社員にもたらします。
例えば、ヘルシーなお惣菜をオフィスで安価に購入できるサービスを導入した企業では「手軽に栄養バランスの良い食事が摂れるようになり嬉しい」と社員から好評で、健康意識も向上したといいます。
社員同士が健康メニューの情報交換をするなどコミュニケーションが活性化する効果も報告されており、職場の一体感醸成にもプラスに働きます。
以上のように、管理栄養士と協働することで専門性にもとづく効果的な施策を展開でき、社員の健康管理を総合的にサポートできます。
それでは次に、これらを実際に実践した福岡のA社の成功事例を見てみましょう。
A社の成功事例:管理栄養士と連携した社員健康サポート
福岡市に本社を置くIT企業のA社(社員数200名規模)は、近年健康経営に本格的に乗り出した企業の一つです。
ここでは、A社が管理栄養士と連携して社員の栄養管理に取り組んだ事例を、課題・施策・成果の流れでご紹介します。
課題:社員の食生活の乱れと健康リスクの顕在化
A社では数年前、社員の定期健康診断の結果に課題が浮き彫りになりました。
30代~50代の男性社員を中心に内臓脂肪型肥満(いわゆるメタボリックシンドローム)予備群が増加し、血中コレステロールや血圧が基準値を超えるケースも散見されたのです。
また、アンケートを取ったところ
「普段の昼食はコンビニ弁当やパンで簡単に済ませている」
「仕事が忙しく夕食が深夜になる」
といった声が多く、食生活の乱れが社員の健康リスクを高めていることが分かりました。
実際に一部の社員からは「疲れやすく午後の集中力が続かない」との自己申告もあり、栄養バランスの偏りが日々の業務パフォーマンスに影響している可能性が指摘されました。
さらに、有志の社員で食習慣に関するヒアリングを行ったところ、「一人暮らしで野菜不足」「朝食はコーヒーだけで済ませる」といった生活実態も明らかになりました。
A社の人事部は、これらの課題を放置すれば将来的に生活習慣病の発症や病欠の増加につながり、企業としての生産性低下や医療費負担増にも直結しかねないと危機感を持ちました。
施策:管理栄養士と協働した食生活改善プログラムの導入
課題を受けて、A社は早速社内プロジェクトチームを立ち上げました。
人事・総務担当者に加え、外部から管理栄養士資格を持つ専門家を招聘し、社員の食生活改善プログラムの企画・実行に乗り出したのです。具体的には、次のような施策を段階的に導入しました。
健康社員食堂「Aカフェ」の開設
社員が栄養バランスの良い食事を手軽にとれるよう、社内に簡易社員食堂スペースを新設しました。
管理栄養士が監修した週替わりメニューを提供し、主菜・副菜・汁物まで野菜中心の献立を用意しました。
例えばある日のメニューは、雑穀米に魚の煮付け、ほうれん草のお浸しといった内容で、塩分や脂質を抑えつつ満足感のある食事を実現しました。
社員食堂を持たない中小企業でも導入しやすいように、冷蔵庫設置型の社食サービス(ヘルシーなお惣菜を1品100円で購入できるシステム)も活用し、勤務シフトの関係で食堂営業時間に間に合わない社員でも24時間好きなタイミングで健康的な食事を入手できる環境を整えました。
管理栄養士による個別栄養カウンセリング
健康診断でメタボ予備群と判定された社員や、アンケートで食生活に不安を感じていると回答した社員を対象に、管理栄養士との個別面談を実施しました。
面談では日々の食事内容や生活リズムをヒアリングし、一人ひとりに合わせた改善アドバイスを提供しました。
例えば
「朝食を取りやすくするため前夜に下準備をする」
「昼食にタンパク質と野菜を必ず一品ずつ加える」
「間食にはナッツやヨーグルトを利用して菓子類を減らす」等、
具体的で実行しやすい提案を行いました。
加えて、面談後もチャットツール等で気軽に相談できる栄養相談窓口を設置し、社員が継続して専門家のフォローを受けられる体制を整えました。
食育セミナー・イベントの開催
全社員対象に、年に数回のペースで健康食セミナーやイベントを開催しました。
テーマは「疲労回復に効く食べ方」「デスクワーカーのための間食術」「減塩クッキング講座」など多岐にわたり、管理栄養士が講師となって実践的な知識を伝授しました。
希望者には野菜ソムリエを招いた料理教室も実施し、楽しみながら栄養知識を深める機会を提供しました。
さらに社内報や掲示板で毎月「栄養だより」を発信し、季節の食材や簡単ヘルシーレシピを紹介するなど、日常的に食と健康への意識喚起を行いました。
ヘルスケアアプリの活用とチーム対抗戦
社員の自主的な参加を促すため、スマートフォンの食事記録アプリを導入し希望者に配布しました。
毎日の食事内容を記録すると自動で栄養バランス評価が表示されるもので、管理栄養士もそのデータを共有してフィードバックを提供しました。
また、部署対抗の健康チャレンジとして「野菜摂取量アップチャレンジ」「歩数チャレンジ」と組み合わせ、ゲーム感覚で楽しめる仕掛けを作りました。
例えば、1ヶ月間の累計野菜摂取量を部署ごとに競い合い、優勝チームにはヘルシーランチ無料券を進呈するといった取り組みです。
こうした遊び心のあるイベントは社員のモチベーションを高め、健康づくりを前向きに継続する風土づくりに役立ちました。
成果:社員の健康指標が改善し企業価値も向上
これらの施策を1年間継続した結果、A社では着実な成果が現れました。
まず、定期健康診断の数値に明確な改善が見られました。
メタボリックシンドロームの該当者数は前年より40%減少し、特定保健指導の対象者(血圧・血糖・脂質異常のリスク保有者)も大幅に減少しました。
平均BMI値は全社で0.5ポイント低下し、特に食生活が乱れがちだった若手社員の体脂肪率に顕著な改善が認められました。
社員アンケートでは
「朝食を週にほとんど摂っていなかったが、会社の取り組みを機に習慣づいた」
「野菜中心の食事を心がけるようになり、体調が良くなった」
といった前向きな声が多数寄せられています。
中には
「半年で体重が5kg減り血圧も正常化した」
という社員もおり、管理栄養士のアドバイスによる生活改善効果がうかがえます。
業務面でも嬉しい変化がありました。
上司からは
「午後の眠気を訴える社員が減り、会議中の発言が活発になった」
「テレワーク中でも食事内容を報告し合うなど、健康を意識したコミュニケーションが増えた」
との報告があり、社員の生産性向上やチームワークの強化につながったとの評価がされています。
実際、全社の年間総病欠日数は前年に比べて約20%減少し、有給休暇の取得日数も増加傾向が見られました。
これは社員が心身ともに健やかに働けている証拠と言えるでしょう。
さらに、A社はこれらの功績が評価され、2024年度「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」に初めて認定されました。
社内での地道な努力が対外的にも評価されたことで、企業としての信用力やブランドイメージが向上し、人材採用の面でも「社員の健康を大切にする会社で働きたい」と入社を志望する応募者が増えるといった好循環が生まれています。
まさに社員も企業も健康になれるWin-Winの成果が得られたと言えるでしょう。
まとめ:健康経営で福岡発の元気な企業づくりを
A社の事例は、管理栄養士と連携した食生活支援が健康経営の成功につながることを示す好例でした。
社員の栄養管理を充実させることで、短期的な健康指標の改善だけでなく、生産性向上や企業イメージアップなど多面的な効果が得られることが分かります。
福岡は活気あるビジネス都市であり、人材確保や組織力強化の重要性がますます高まっています。
そうした中で社員の健康を土台から支える健康経営は、企業競争力を高める戦略として欠かせません。
健康経営の推進には経営層のコミットメントが不可欠ですが、まずはできる範囲から着手することが大切です。
例えば
「毎週○曜日は野菜たっぷり社食Day」
「管理栄養士による健康コラムを社内配信」
といった小さな施策でも、継続することで大きな成果につながるでしょう。
幸い福岡には専門知識を持つ管理栄養士や健康経営を支援する団体が多数存在しますので、それらと積極的に連携しながら自社に合った取り組みを進めてみてください。
最後に強調したいのは、健康経営は「継続は力なり」の取り組みであるという点です。
社員の健康意識と行動は一朝一夕で変わるものではありませんが、経営側の根気強い支援と専門家のサポートによって必ずや良い方向へと変化していきます。
福岡発のA社の成功事例に続き、ぜひ皆様の企業でも管理栄養士と二人三脚で社員の健康サポートに取り組んでみてはいかがでしょうか。
社員がいきいきと働き、企業も持続的に成長できる——そんな理想的な職場づくりを、健康経営によって実現していきましょう。
2025年4月24日 カテゴリー: 未分類