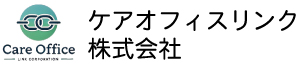中小企業の経営者や総務・人事担当者にとって、経理・人事・庶務などのバックオフィス業務をどのように運営するかは大きな課題です。
限られた人員で日々の事務作業を回している企業も多く、従業員100名規模の中小企業では経理と総務を一人で兼任するケースも珍しくありません。
こうした状況下で、
「専門業者にアウトソーシングすべきか、それとも新たに社員を自社採用すべきか」
という判断に頭を悩ませている方も多いでしょう。
採用には時間と採用コストがかかるうえ、せっかく採用してもすぐに辞められてしまう退職リスクもあります。
一方で、外部委託には情報管理や品質の面で不安を感じることもあるかもしれません。
本テーマでは、アウトソーシングと自社採用のメリット・デメリットを整理し、特に福岡中小企業がバックオフィス体制を検討する際のポイントについて解説します。
アウトソーシングのメリット・デメリット
まず、バックオフィス業務をアウトソーシング(外部委託)する場合のメリット・デメリットを見てみましょう。
アウトソーシングとは、自社の業務プロセスの一部を外部の専門業者に委託することです。
近年では経理代行や人事労務の代行など、中小企業向けの様々なバックオフィスBPOサービスが登場しています。
アウトソーシングのメリット
人件費・採用コストの削減
最大のメリットの一つはコスト面です。
新たに社員を雇用すると、給与や社会保険料など毎月の固定費に加え、求人募集や面接にかかる採用コストが発生します。
アウトソーシングであればこれらの費用を抑えることができ、必要な業務量に応じて契約するため無駄がありません。
専門知識・スキルの活用
外部の専門業者には、各分野(例:経理、法務、人事労務など)のプロフェッショナルが揃っています。
そのため、自社内に専門人材がいなくても高品質なバックオフィス業務が実現できます。
例えば、最新の法改正に対応した人事手続きや、クラウド会計ソフトの活用など、専門家ならではの知見を活かせます。
リソースの柔軟な調整
アウトソーシングは必要に応じてサービスの範囲や量を調整しやすい点も魅力です。
繁忙期には依頼する作業を増やし、閑散期には縮小するといった柔軟な対応が可能で、自社で雇用する場合のように常に一定の人件費がかかる心配がありません。
季節的な業務量の変動やプロジェクト単位での対応に適しています。
コア業務への専念
煩雑なバックオフィス業務を外部に任せることで、社内のスタッフは売上につながるコア業務に集中できます。
限られた経営資源を本業に振り向け、生産性を高められるのは中小企業にとって大きな利点です。
「雑務に追われて戦略策定の時間が取れない」という状況を避け、経営者や従業員の負担軽減につながります。
人事リスクの低減
社員を雇用すると、その人が病欠したり産休に入ったり、最悪退職してしまうリスクがあります。
アウトソーシングなら、契約先の企業がサービス提供者を確保してくれるため、特定の担当者に依存せずに業務を継続できます。
社員の突然の退職による業務停滞リスクを抑えられるのは、小規模組織にとって安心材料です。
アウトソーシングのデメリット
社内ノウハウが蓄積されない
業務を外部に任せきりにすると、自社内に経験や知識が残りません。
例えば、外注している間に培われた効率化の工夫や専門的な知識が、自社メンバーに共有されないままになります。
その結果、将来的に内製化しようとしてもノウハウ不足で苦労する可能性があります。
コミュニケーションの難しさ
外部スタッフとのやり取りになるため、社内の人間同士のように気軽に相談・指示がしにくい面があります。
業務のニュアンスや細かな要望を伝えるのに時間がかかったり、伝言ゲーム的なズレが生じたりするリスクがあります。
特にバックオフィス業務は自社独自のルールや運用が多い分、意思疎通には工夫が必要です。
情報漏洩などセキュリティリスク
社外に機密情報や個人情報を提供する以上、情報漏洩のリスクはゼロではありません。
信頼できる業者を選定し、契約書で守秘義務を明確にするなどの対策が必要です。
また、自社内で管理していない分、万が一トラブルが起きた際に把握や対応が遅れる懸念もあります。
業務コントロールの難易度
業務プロセスを自社で直接管理できないため、進捗状況や細かな業務フローの把握が難しくなります。
アウトソーシング先に任せた業務が予定通り行われているかを定期的に確認するなど、マネジメントの手間が発生します。
場合によっては、「依頼した仕事の範囲外なので対応できない」といった制約に直面する可能性もあります。
自社採用のメリット・デメリット
次に、自社でバックオフィス要員を採用し、社内で業務をまかなう場合のメリット・デメリットを確認します。
自社採用とは、新たに正社員や契約社員を雇い入れて自社内で業務処理を行う方法です。
伝統的には多くの企業で採用されてきた形態ですが、現代の中小企業にとってはどのような利点と課題があるでしょうか?
自社採用のメリット
円滑なコミュニケーション
社員として社内に人材がいれば、日々のコミュニケーションや突発的な指示出しがスムーズに行えます。
顔を合わせて打ち合わせができ、細かなニュアンスも共有しやすい環境は、業務の正確性やスピード向上につながります。
また、他部署との連携や社内の情報共有も取りやすくなります。
自社内での情報管理
機密情報や顧客データなどを自社内の人間だけで扱えるため、情報漏洩リスクを抑えやすく安心です。
外部に出さないことでセキュリティコントロールが利き、万が一問題が起きても社内で迅速に対処できます。
重要データを社外に預けることに抵抗がある場合、内製化しておけばリスクコントロールがしやすくなります。
企業文化・ノウハウの蓄積
同じ社員が長期にわたり業務に携わることで、自社のビジョンや企業文化をバックオフィス業務にも反映できます。
社風を理解した上で業務改善を提案してくれたり、現場の声を経営にフィードバックしてくれる可能性もあります。
また、業務を通じて得た知識やノウハウが社内に蓄積されるため、組織学習の観点でもメリットがあります。
臨機応変な対応力
社員であれば業務範囲を柔軟に拡大したり、急な頼み事にも対応してもらいやすいでしょう。
例えば、通常は総務担当の社員に、イベント時には受付を手伝ってもらうなど、小規模企業ならではの「マルチタスク」な活躍も期待できます。
契約で定められた範囲以上のことは基本対応できないアウトソーシングに比べて、社内スタッフの方が融通が利く場面も多いです。
自社採用のデメリット
人件費負担の増加
新規に人材を雇用すると、毎月の給与に加えて賞与や各種手当、福利厚生費など継続的なコストが発生します。
例えば年収300万円程度で雇用すると、企業側の社会保険負担等を含め年間で数百万円の人件費負担となります。
中小企業にとってこの固定費増は大きなプレッシャーです。
さらに、業務量が減っても容易に人員削減ができないため、閑散期には人件費が無駄になる可能性もあります。
採用コストと手間
良い人材を採用するには、求人広告の掲載費用や応募者対応の時間、面接の労力など多大な手間がかかります。
採用が長引けばその分コストもかさみますし、ようやく採用しても期待したスキルを備えていないミスマッチのリスクもあります。
中小企業では知名度が低いために応募自体が集まらず、採用活動自体に苦戦するケースもあるでしょう。
社員の退職リスク
苦労して採用・育成した社員が、家庭の都合や他社への転職などで退職してしまう可能性はゼロではありません。
特にバックオフィス担当者が1名体制の場合、その社員が辞めてしまうと業務知識がごっそり抜け落ちてしまい、業務が滞るリスクが高まります。
引き継ぎがうまく行われなかったり、後任探しに再びコストと時間がかかるといった事態にもなりかねません。
人事・労務トラブルへの対応
人を雇用する以上、避けられないのが人事労務面の対応です。
たとえば職場の人間関係の悩みやハラスメント防止、残業管理、有給管理など、雇用した社員を守り適切に働いてもらうための体制整備が必要です。
こうした対応には専門知識が求められる場面も多く、小規模企業では経営者や少数の管理者に大きな負担となります。
また、万一解雇などの事態になれば法的な手続きやリスクにも向き合わねばなりません。
福岡中小企業が考慮すべきポイント
では、福岡の中小企業がバックオフィス体制を検討するにあたり、どのようなポイントに注目すべきでしょうか?
地域特性や自社の状況を踏まえ、以下の点を考慮することが重要です。
地域の採用環境と人材確保の難易度
福岡は近年スタートアップ支援にも力を入れており、中小企業やベンチャー企業が増加しています。
その一方で、優秀な人材の奪い合いは都市圏同様に激しく、特にバックオフィス分野で経験豊富な人材を確保するのは容易ではありません。
実際、福岡のある製造業A社では、経理担当者の採用に半年以上かかり、最終的に希望するスキル要件を満たす人材が見つからなかったというケースもあります。
こうした場合、採用活動に費やした時間とコストが無駄になってしまいます。
地元で人材確保が難しいと感じる場合は、アウトソーシングも視野に入れ、広く人材リソースを活用することが求められます。
コスト比較と企業規模に合った選択
自社の予算や規模に照らして、アウトソーシング費用と人件費の比較検討も欠かせません。
福岡の中小企業B社(社員20名)は、経理業務をアウトソーシングしたところ、月額固定費用は発生したものの、年間トータルでは正社員1名分の人件費より低く抑えられました。
一方で、社員数5名のC社では、外部委託よりもパートタイム社員を直接雇用した方が安価に運用できています。
このように、企業規模や業務量によってコスト効率の良い方法は異なります。
自社の状況に応じてシミュレーションを行い、採用コストや外注費用、将来的な業務拡大の見込みなどを踏まえて判断しましょう。
ローカルならではの利点・課題
福岡のように地域コミュニティが強い土地では、地元の事情に詳しい人材やサービスを活用できる利点があります。
例えば、福岡特有の商習慣やネットワークを理解したバックオフィス担当者がいれば、地域に根ざした細やかな対応が可能です。
また、同じ福岡県内のアウトソーシング業者であれば対面で打ち合わせしやすく、信頼関係を築きやすいでしょう。
一方で、地方ならではの課題として、選択肢が首都圏ほど多くないことも考えられます。
専門性の高い業務については、福岡以外(東京など)のサービスをリモートで活用することも視野に入れ、最適なリソースを見極めることが重要です。
自社の事業戦略との適合
最後に、アウトソーシングか自社採用かの選択は、自社の事業戦略や将来展望にも影響されます。
例えば、将来的にバックオフィス部門を社内の中核として育成したいのであれば、時間をかけてでも自社採用でノウハウを蓄積する意義があります。
一方、事業拡大のスピードを重視し、バックオフィスに割くリソースを極力抑えたい場合は、アウトソーシングで即戦力を得る方が得策でしょう。
福岡発のスタートアップ企業でも、初期は外部の士業やサービスに委託し、事業が軌道に乗ってから内製化に切り替えるといった段階的な戦略をとる例が見られます。
自社の成長ステージやビジョンに照らして、最適な体制を検討することが肝要です。
さいごに
アウトソーシング vs 自社採用は一長一短であり、どちらが「正解」という絶対的な答えはありません。
中小企業のバックオフィス運営において重要なのは、自社の規模・業務量・予算・求めるクオリティなどを総合的に考慮し、最適な方法を選ぶことです。
アウトソーシングの柔軟性や専門性は魅力的ですが、社内にノウハウを蓄積することやきめ細かな対応が必要な場合には、自社採用の方が適しているでしょう。
場合によっては、
「給与計算と社会保険手続きはアウトソーシングし、日常の総務対応は社内スタッフが行う」
というように両者を組み合わせて利用する選択肢もあります。
重要なのは、自社の課題を明確にした上で、外部の専門家や支援機関とも相談しながら最善策を講じることです。
福岡の中小企業においても、経営環境や人材市場の変化に応じて柔軟にバックオフィス戦略を見直す姿勢が求められます。
本テーマの内容を参考に、自社にとってベストな体制を検討し、効率的かつ安定したバックオフィス運営を実現してください。
2025年5月2日 カテゴリー: 未分類